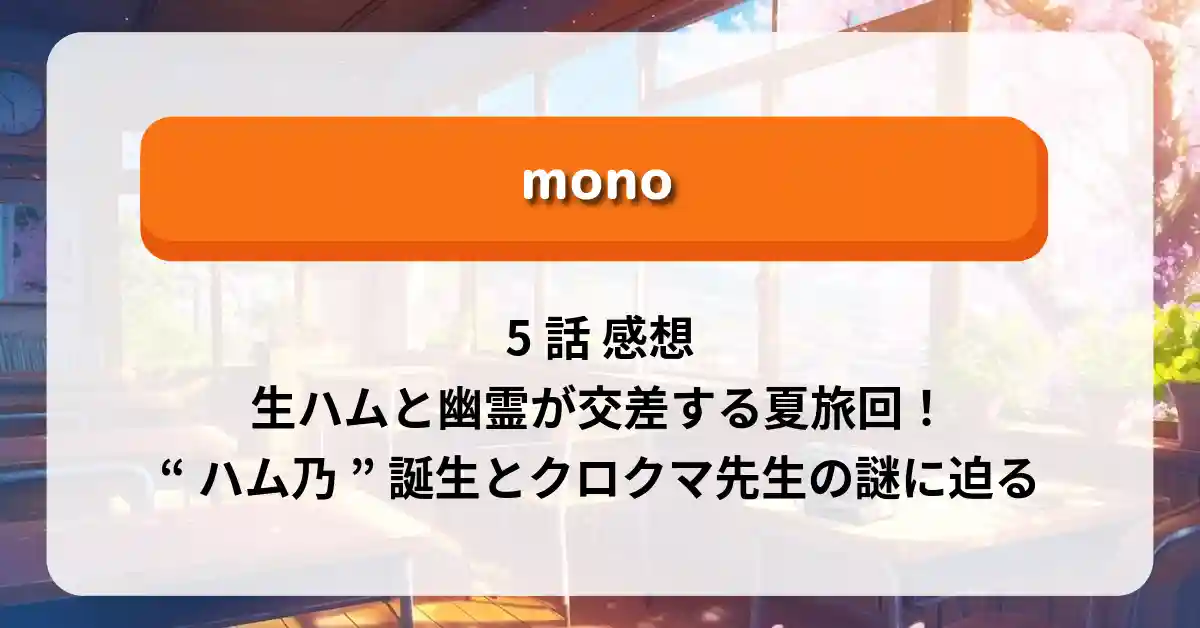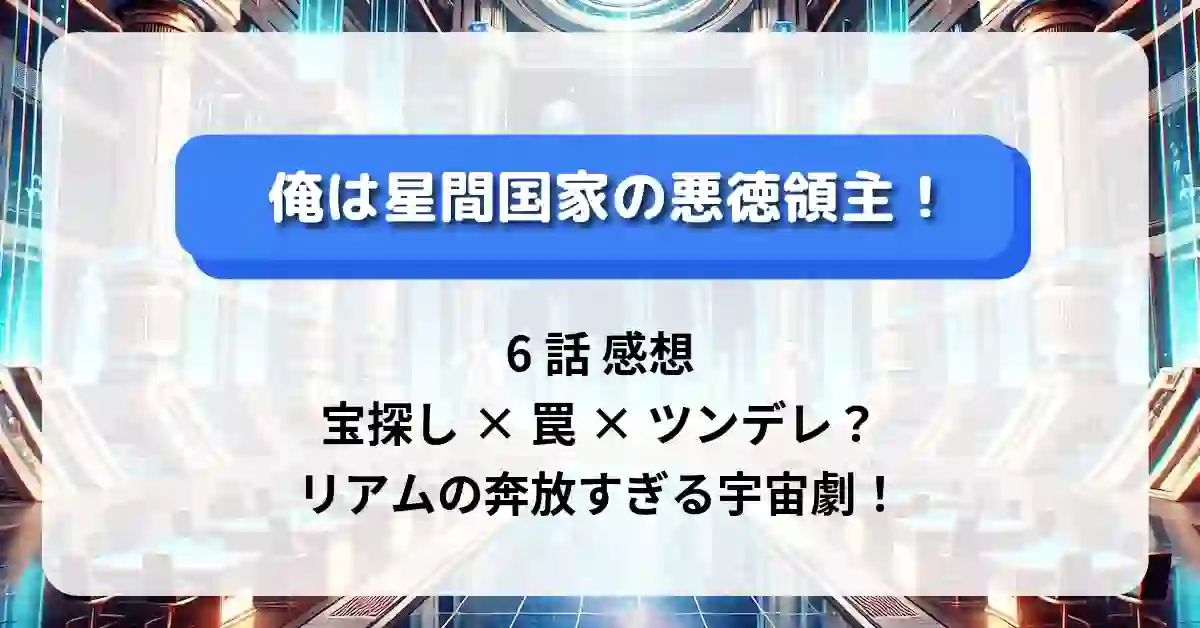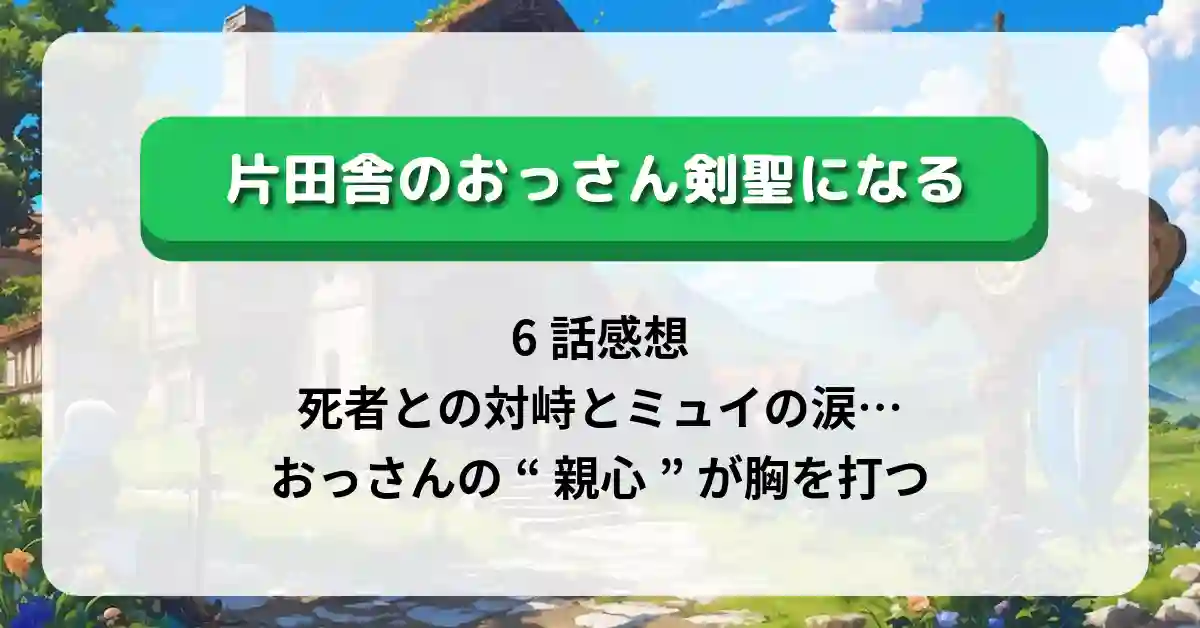『mono』第5話は、生ハムを求めて山梨を巡る旅と、まさかの心霊憑依事件という異色の構成が話題に。
前半は“ハム乃”こと春乃の爆買いが笑いを誘い、後半はクロクマ先生の登場で物語がホラーへと急展開。
旅情・ギャグ・ホラーが絶妙に溶け合う今話は、作品の幅広い魅力を再確認させてくれます。
ロケ地のリアルさやカメラ演出、伏線回収の巧みさなど、多角的に見どころ満載なエピソードでした。
アニメレビュー歴10年以上の筆者が、その魅力をじっくりと読み解きます。

ハム旅かと思ったら、まさかの幽霊回!?展開飛びすぎでしょ!

ほんとに(笑)でもクロクマ先生のキャラ濃すぎて、逆に癖になるかも。どんな話だったか見ていこう!
※この記事は2025年5月11日に更新されました。
mono 5話 感想|旅情とホラーが融合した異色のエピソード
「mono」第5話では、Aパートが“生ハム探しのグルメ旅”、Bパートが“心霊スポットでの憑依事件”という大胆な構成で展開されました。視聴者は軽妙な旅の空気感から一転、不意に訪れる怪異に驚かされつつ、キャラクターの魅力と物語の広がりに引き込まれたことでしょう。
生ハム探しで始まる“夏の避暑地グルメ旅”
第5話の前半は、春乃が楽しみにしていた生ハムが祖母の焼きそばの具になってしまうという事件から始まります。そこから一同は八ヶ岳のハムを求めて山梨へと旅立ち、避暑地・清里や展望カフェを訪ね歩く構成となっています。
旅情あふれるシーン構成に加え、ロケ地の空気感を伝える背景美術と、視覚的な開放感に満ちた描写が印象的です。夏のスキー場、展望リフト、メリーゴーランドなど、地元の魅力が随所に織り込まれています。
さらに、部員たちの減量中エピソードとの繋がりや、カメラ要素が添えられることで、“観光”と“シネフォト部の活動”が緩やかに融合。Bパートへの布石としても機能していました。
“ハム乃”爆誕!キャラ変すら楽しむ春乃の魅力
ハムを買いすぎた春乃が“ハム乃”と呼ばれ、エンディングクレジットにまで影響を与えるという流れは、視聴者に強烈な印象を残しました。これはギャグだけでなく、キャラクターの立ち位置を曖昧に広げる「きらら系」らしい遊び心でもあります。
CV・上田麗奈さんの緩やかで憂いを含んだ演技が、春乃のマイペースさと疲弊感を絶妙に表現し、そのテンション感が“ハム乃”というあだ名と化学反応を起こしていました。
また、本人は気付かぬまま他者に突き動かされていく彼女の様子には、現代の社会人像すら感じられます。まるで“趣味に逃げながらも現実を少しだけ受け入れている姿”が、見る人の共感を呼ぶのでしょう。
カメラに映った幽霊とクロクマ先生の登場
後半は打って変わって、春乃の部屋に仕掛けられたアクションカムに幽霊が映るというホラー展開に。過去回で訪れたトンネルでの伏線が回収され、幽霊の正体も薄っすらと明かされていきます。
そこで登場するのが、霊感を持つゴスロリ漫画家・クロクマ先生。そのビジュアルと属性の過積載ぶり、そしてCV・羊宮妃那さんによる登場早々の嘔吐演技など、インパクトの塊です。
ホラーでありながら、過剰に怖がらせない“ライトな怪談”の空気が保たれており、あくまでmonoらしい“まったり+非日常”の世界観が崩れません。この絶妙なバランス感覚が、第5話の大きな魅力と言えるでしょう。
旅先描写の妙|八ヶ岳・清里の風景と空気感をどう演出したか
「mono」第5話の見どころの一つが、避暑地・清里や八ヶ岳といった舞台の美しい描写です。背景美術や構図、空気感の再現に優れており、ただの観光描写にとどまらない臨場感を与えてくれました。特に旅先での会話や食事風景、リフトからの眺望は、アニメでありながらも“行ってみたくなる”リアリティをもって描かれています。
360度カメラによる構図と自然描写のリアリティ
本作の撮影表現には、360度カメラを意識した構図が多く登場します。これは単なる映像技法に留まらず、視聴者がその場に“同行している感覚”を生み出す装置として機能しています。生ハムを求めて立ち寄る土産屋、展望デッキからの広がる景色など、360度に展開される風景は旅番組さながらの没入感を演出。
特に、空撮風のバス走行シーンや魚眼レンズ的なレイアウトは、他のきらら系アニメではあまり見かけないチャレンジングな手法です。視覚的なアクセントが旅情をより濃密にするという点で、本作ならではの映像美が感じられました。
展望リフトと廃墟の演出が物語に与える余韻
避暑地として描かれた清里では、オフシーズンのスキー場や展望カフェといった施設が舞台となり、通常の観光アニメとは一線を画す“静けさ”が際立っていました。特に、展望リフトに揺られながらのカットや、バブル遺産の廃墟に向かって手を合わせるシーンは、儚さや時間の流れを印象づけます。
人の営みのあとが残る場所での沈黙や、少女たちの“写真に収める”という行為が重なることで、日常の向こうにある“記憶”へのアクセスが可能になる。このような演出は、まさに“mono”というタイトルに込められた「モノ(記録・記憶・残像)」という概念と深くリンクしているように思えます。
“心霊スポット憑依事件”から読み解く本作のテーマ性
「mono」第5話の後半では、突如としてホラー要素が現れます。可愛らしく穏やかな日常系アニメにおいて、幽霊という存在が登場することで物語に新たな奥行きが加わりました。これは単なるギャグではなく、作品全体に流れる“過去との対話”や“記憶の可視化”という深いテーマにもつながっています。
クロクマ先生のキャラ性と除霊展開のギャップ演出
心霊現象の解決役として登場したのが、ゴスロリ姿の売れっ子ホラー漫画家・クロクマ先生。彼女の登場は視聴者に強烈な印象を与えました。高級車から降り立ち、初手で嘔吐し、幽霊の気配を察知して“部屋の掃除”を指示するなど、その属性過積載ぶりと演出のギャップはまさに笑いと驚きの融合です。
しかし、このユニークな登場は笑いを誘うだけではなく、「見える人」だけが感じ取る異界との接点を象徴しています。クロクマ先生の存在を通して、“視えないものを見る感性”がこの作品の裏テーマであることが仄めかされました。
📌クロクマ先生の設定まとめ
| 肩書 | 売れっ子ホラー漫画家(累計650万部) |
| 趣味・嗜好 | 猫好き・ゴスロリファッション愛好家 |
| 霊感 | アクションカム映像で霊の存在を即座に察知 |
| 登場時の印象 | 高級車・初手ゲロインという強烈な登場 |
伏線としてのトンネル回と、霊の存在の扱い方
今回の幽霊は、過去回での心霊スポット訪問が伏線となっていました。春乃に憑依した少女の霊は、生前に飼っていた鳥と春乃の愛鳥が似ていたという理由でついてきたというエピソードが明かされます。この設定により、恐怖というよりも“未練と愛着”を感じさせる幽霊像が描かれています。
幽霊との別れに「またね」と返されるシーンは、単なる除霊ではなく“心のやりとり”であり、モノローグのように静かでやさしい感情の往復が本作らしい余韻となって残ります。これは単なる怪談ではなく、「過去の記憶とどう向き合うか」という本質的な問いかけを孕んでいるように思えるのです。
SNSでの反応と考察|“ハム乃”ネタと意外な盛り上がり
第5話は放送直後からSNSを中心に大きな反響を呼び、「#ハム乃」が一時トレンド入りするほどの盛り上がりを見せました。特に視聴者の注目を集めたのは、春乃の改名ネタと幽霊騒動の二本立てという異色の構成。それぞれのシーンにユーモアと違和感の絶妙なバランスがあり、観た人の記憶に強く刻まれました。
エンディングまで貫かれる“ハム乃”いじりのセンス
SNSでは「ハム乃」という呼び名が拡散され、エンディングテロップで本当に“秋山ハム乃”と表記されたことで爆笑の渦を巻き起こしました。こうした細かい演出は、視聴者への遊び心として機能しており、作品の“ゆるさ”と“自由度の高さ”を象徴しています。
「あだ名が公式化する」というメタ的なギャグは、視聴体験を一段深くするクリエイティブな仕掛けとも言えるでしょう。小ネタながらも丁寧な作りが、ファンの二次創作意欲にも火をつけているようです。
読者の声から見える「mono」への共感ポイント
SNSの反応を見ると、「春乃の気だるげな日常に共感した」「写真関係なく旅する感じがリアル」「クロクマ先生また出てほしい」といった声が多く見られました。これらはすべて、「mono」という作品が持つ“抜け感”と“心地よい脱力”に対する共感の表れです。
シネフォト部の活動そっちのけで旅と食と怪異を満喫するという流れが、忙しい日常に疲れた現代人の“理想の逃避”として映っているのかもしれません。まるで“ゆるやかな無駄”に価値を見出すようなこの空気感が、今の視聴者にフィットしているのでしょう。
“ゆるホラー”としての魅力|笑いと恐怖の絶妙なバランス
「mono」第5話は、日常と非日常が同居する“ゆるホラー”という新たな境地に踏み込みました。決して視聴者を突き放すような怖さではなく、あくまでキャラクターたちの空気感の中で、幽霊という存在がユーモラスに扱われることで、独自の心地よい緊張感が生まれています。
ゴスロリ漫画家という属性盛りのキャラ造形
クロクマ先生という新キャラは、ゴスロリ・霊感体質・猫好き・売れっ子漫画家という設定が重なった、ある意味で本作随一の個性派キャラです。その過剰なスペックをあくまで“静かなテンション”で演じることで、不気味さよりも親しみやすさが勝るバランスが生まれています。
特にCV・羊宮妃那さんのやや脱力した芝居が、非日常の中にある“日常の余白”を見事に表現していました。トンネルの除霊シーンでも過度にドラマチックにならず、どこか“エモい”余韻を残したのは、キャラクター造形と演技の妙といえるでしょう。
ホラー演出に漂う“昭和怪談的ノスタルジー”
第5話のホラー要素は、「ダンダダン」や「見える子ちゃん」にも通じる現代的な怖さを感じさせつつ、どこか昭和の怪談的な“やさしい怖さ”も持ち合わせていました。これは廃墟やトンネルといった舞台選びにも起因しています。
“霊がついてくる”という現象に悲しみと哀愁をにじませ、それを軽やかな会話劇と併走させる構成が、ジャンルを横断する面白さを生んでいました。ホラーが怖さだけでなく、キャラの内面や過去との接点を掘り下げるツールになっている点も、本作の深みを象徴しています。
昭和怪談的ノスタルジーとは?
昭和の怪談番組や怪奇特集においては、恐怖の中に“寂しさ”や“未練”といった感情が織り込まれることが多く、ただ怖がらせるのではなく“哀愁を感じさせる怪異”が主流でした。mono第5話の幽霊も、少女の生前の想いや愛着が動機となっており、その描写はまさに古典怪談の再解釈といえるでしょう。現代の「ビックリ系」ではなく、静かに心を揺らす作りが印象的です。
まとめ|mono第5話は“感性を刺激する旅と霊性の物語”
「mono」第5話は、ただのグルメ旅や心霊騒動では終わらない、日常の中にある非日常を丹念に描き出したエピソードでした。ハムを巡る笑いと、幽霊との交流ににじむ哀しさ。その両方を違和感なく共存させた演出力と構成力に、作品の懐の深さが光ります。
クロクマ先生という新たな風が吹き込まれ、春乃=ハム乃という愛されキャラの再定義、トンネルという“記憶の舞台”での対話まで、全体を通してテーマと感情が丁寧に繋がっていました。
旅・食・幽霊…とジャンルを越境する構成でありながらも、“monoらしさ”が一貫していたのは、カメラという媒体を通じて「残すこと」を問い続けているからでしょう。ゆるやかに進む物語の中に、人生と記憶を紡ぐ静かな強さが宿っていました。
◆ポイント◆
- グルメ旅と心霊体験の二本立て
- “ハム乃”ネタがSNSで話題
- クロクマ先生の登場が衝撃的
- 心霊描写に温かみがある演出

ご覧いただきありがとうございます!
ハム旅から心霊憑依まで、振れ幅の広さが印象的でしたね。
春乃の“ハム乃”化やクロクマ先生の登場など、話題が尽きない回でした。
SNSでのシェアや感想もぜひ聞かせてください!