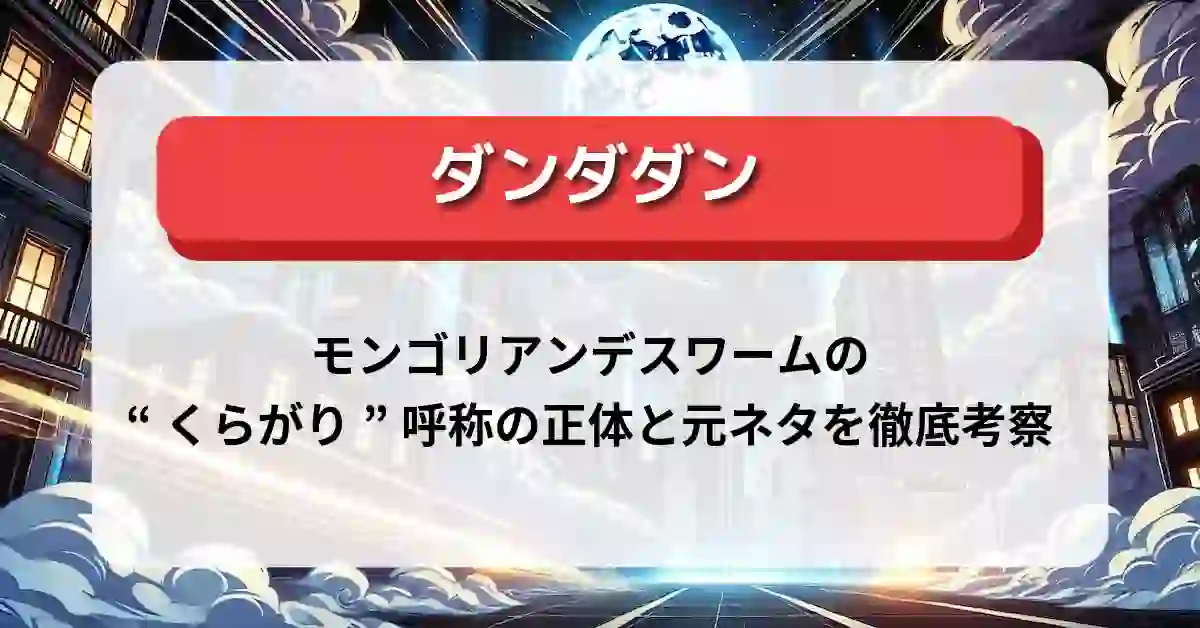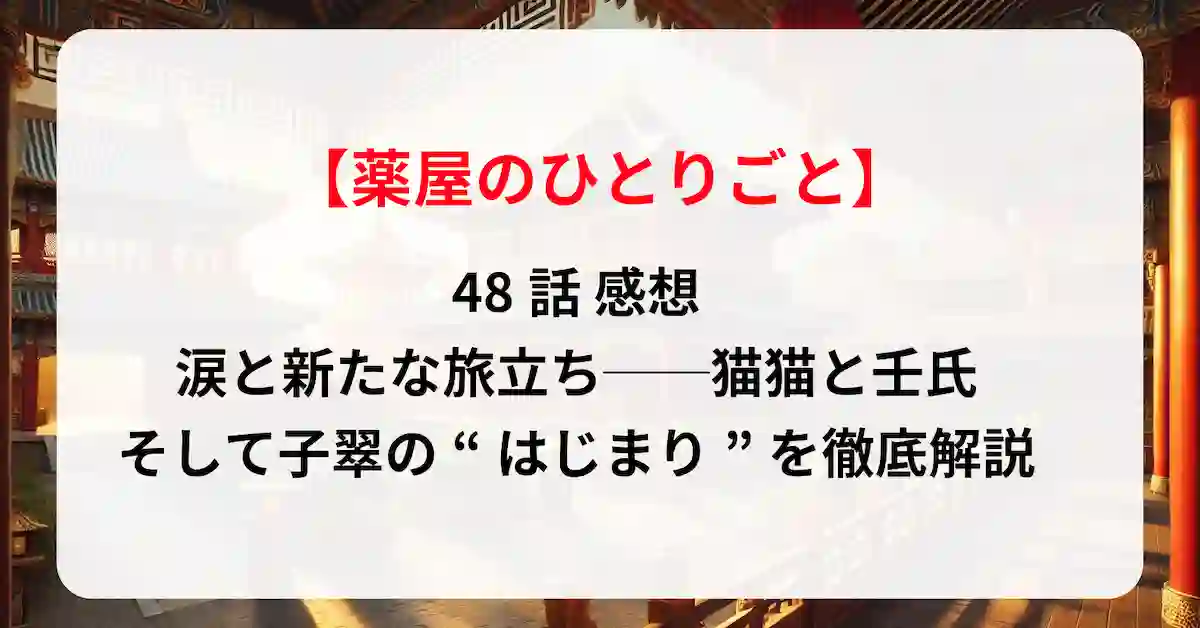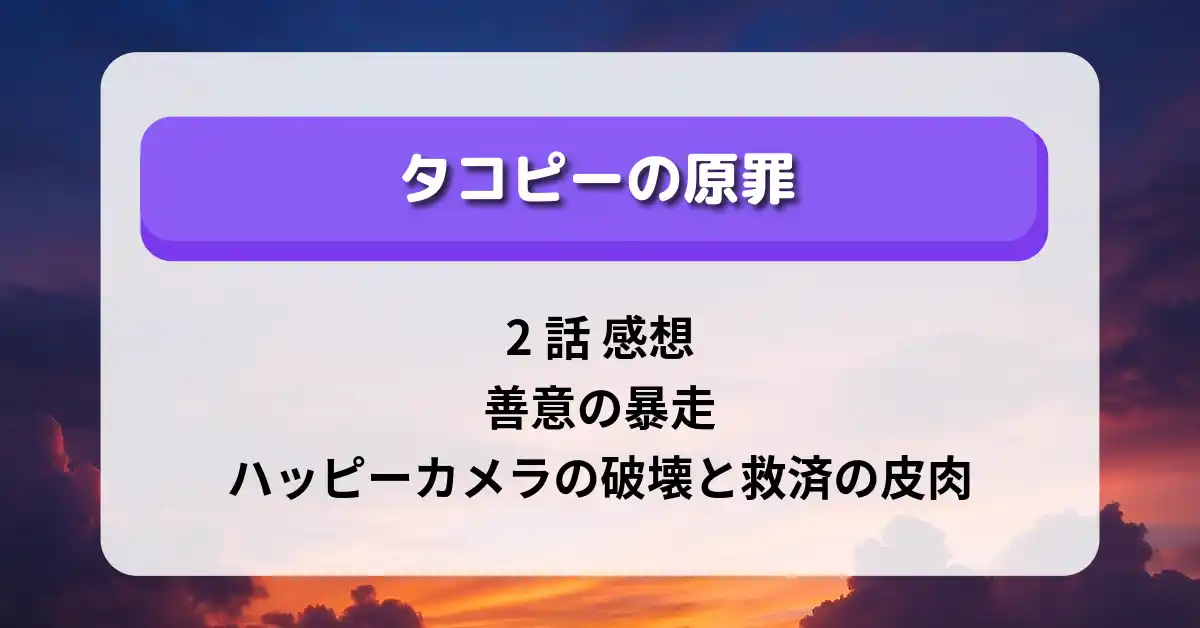巨大なミミズ状の化け物、モンゴリアンデスワーム。
その異様な存在を前に、ターボババアが放った一言──「くらがりか」──に、読者の間でざわめきが走りました。
この“くらがり”とは一体何なのか?
実はこの名前、日本各地に伝わる「暗がりに潜む大蛇」の伝承に通じており、『ダンダダン』ではそれを下敷きに設定が練られているようです。
この記事では、「くらがり」と呼ばれた理由やその正体、日本の伝承との共通点、そしてモンゴリアンデスワームの元ネタに迫っていきます。
※この記事は2025年7月5日に更新されました。
◆内容◆
- ダンダダン「くらがり」の正体がわかる
- モンゴリアンデスワームの元ネタを解説
- 「くらがり」と伝承の共通点がわかる
ダンダダン モンゴリアンデスワーム くらがり 正体とは?冒頭で謎を解く
『ダンダダン』第5巻37話でターボババアがモンゴリアンデスワームを見て発した一言──「くらがりか」。
この台詞は単なる冗談や誤認ではなく、彼女の記憶と経験に根ざした“ある種の正体認識”だったのではないかと考えられます。
本章では、「くらがり」という言葉の意味を紐解きながら、なぜターボババアがモンゴリアンデスワームをそう呼んだのか、その背景と正体を明らかにしていきます。読者が抱く「くらがりって何?」という疑問に、明確な答えを提示するパートです。
ターボババアが「くらがりか」と言ったシーンを振り返る
モンゴリアンデスワームが突如として現れ、主人公たちに襲いかかるシーン。そこでターボババアは一目見て「くらがりか」とつぶやきます。この言葉は明らかに彼女の過去の記憶を引き起こしたリアクションであり、直感的な“認識”と言えるでしょう。
読者から見れば「くらがりって何?」という謎の呼称ですが、ターボババアの中ではすでに同種の存在と遭遇した過去があるように描かれており、ただの見間違いでは済まされない重みがあります。この台詞は物語世界の深層に触れるヒントとなっており、今後の展開を読み解く重要な伏線でもあると考えられます。
#ダンダダン 第13話
— ゲイル (@huraibou_1407) July 4, 2025
ババア達の戦闘センスもさることながら、それらと対等にやり合えるモモ達も大概だなぁ。笑
格闘センスの描写はさすがだw
さて、これ割と詰んでますよね。
あんな化け物に勝てる見立てがまるでないw
そこからの逆転劇をどう描くか?#Dandadan pic.twitter.com/rKw9SVPmEH
「くらがり」と呼ばれた背景と作中の意味
「くらがり」という名前は、『ダンダダン』世界の中でターボババアが持つ“妖怪やUMAに関する知識”の一端として語られます。これは、彼女が過去に遭遇した“異形の怪異”をこの名で記憶していた可能性を示唆しています。
読者目線では唐突に出てきたこの呼称ですが、作中ではあえて「固有名詞」として提示された点がポイントです。日本に伝わる「くらがり淵」や「くらがり沢」といった地名由来の大蛇伝説と対応させると、意味が一気に明確になります。暗闇に棲む未知の存在=くらがりという捉え方が、キャラクターたちの脅威認識とも一致しているのです。
つまり、くらがりとは“未知の怪異に対する人間の名付け”そのものであり、それがターボババアにとってのリアルな実体験として機能していたのでしょう。
ターボババアの発言に込められた意味
- 「くらがり」はターボババアが過去に遭遇した存在の名称と思われる
- 作中で初登場する呼称であり、公式な設定とは別視点のローカル名称の可能性がある
- 妖怪・伝承とUMAが混じる本作ならではの“多重解釈”が可能な台詞
モンゴリアンデスワームの特徴と“くらがり”的正体との融合
モンゴリアンデスワームは、巨大なミミズ状の肉体、毒液のような粘液、電気的攻撃を使うというUMA的特徴を持ちます。これらは一見フィクションに見えますが、実在する伝承「くらがりの大蛇」と驚くほど一致するのです。
特に「甘酒のような液体を吐く」「沼や淵に棲む」「暗がりから現れる」といった特徴は、四国・長野地方の“くらがり伝説”に共通しています。ダンダダンはこの伝承をモチーフに、現代版モンスターとして再構築していると見るべきでしょう。
つまり、ターボババアの「くらがりか」というセリフは、読者が一歩踏み込めば気づく“伝承×現代UMA”の融合を象徴する台詞だったのです。

ターボババアが「くらがりか」って言ったとき、背筋ゾクッときたよな…

あれって昔話の妖怪と繋がってるの!?UMAだけじゃなかったにゃ!

そうそう、今回はその“くらがり”の正体や元ネタを深掘りしてるから要チェックだ!
モンゴリアンデスワームの元ネタを探る:くらがりの伝承とUMA起源
『ダンダダン』に登場するモンゴリアンデスワームは、単なるフィクションの産物ではありません。実はこの存在には、
実在するUMA(未確認動物)としての記録と、日本の妖怪・伝承に通じる共通点が多く含まれています。
本章では、まず「くらがり」の語源や日本の伝承的背景を紹介しつつ、UMAとしてのモンゴリアンデスワームの起源、さらには作品が参照したであろう他文化の怪異との関連性にも踏み込みます。
日本の伝承「くらがり淵の大蛇」「くらがり沢の大蛇」との類似点
「くらがり」という言葉は、実在する地名と大蛇伝承から着想を得たと考えられます。特に四国地方に伝わる「くらがり淵の大蛇」や、長野県の「くらがり沢の大蛇」は、深い森や沼に棲み、毒や粘液を持つ巨大な蛇として語られてきました。
これらの伝承に登場する大蛇は、人の姿をして近づいたり、時には甘酒のような粘液を吐いて人間を溶かすなどの不気味な描写が残されています。こうした性質が、『ダンダダン』に登場するモンゴリアンデスワームと不気味なほど一致するのです。
作者はこうした伝承から「くらがり」の名を借りたことで、単なるUMAでなく“日本的な怪異”としての重層的な恐怖を作品に持ち込んでいると考えられます。
モンゴリアンデスワームというUMAと怪異設定の重なり
モンゴリアンデスワームは、中央アジア・ゴビ砂漠に生息するとされるUMA(未確認動物)で、真っ赤な巨大ミミズ型、毒液や電撃を放つといった特徴で有名です。西洋のUMA図鑑にもたびたび登場する“謎の生物”です。
『ダンダダン』では、このUMAの特徴に加え、日本の「くらがり伝承」の要素を融合させることで、より生々しく恐ろしい存在に仕上げています。単なるUMAではなく、「異界の妖怪」としての側面が色濃く描かれているのがポイントです。
UMAと妖怪の“境界”を超えた描写は、現代的なオカルト表現の巧みさでもあり、読者に強いインパクトを与えました。
📌くらがり伝承とモンゴリアンデスワームの比較
| 名称 | くらがり(伝承) | モンゴリアンデスワーム(UMA) |
| 出現場所 | 沼・淵・暗がり | 砂漠・地中 |
| 攻撃手段 | 甘酒のような粘液、霊的影響 | 毒液、電撃、粘液 |
| 描写される印象 | 大蛇型の妖怪・不定形 | 巨大ミミズ型UMA |
| 文化的起源 | 日本の民間伝承 | 中央アジア・UMA伝説 |
ミニョコンとの類似性:ファンの間で注目される比較対象
作中で「モンゴリアンデスワーム=ミニョコン?」というセリフが明言されたわけではありませんが、読者やファンの間では、南米のUMA“ミニョコン”との類似性が指摘されています。
ミニョコンはブラジルの密林に棲むとされる未確認生物で、赤い巨大ミミズ状、粘液をまとう、姿が不明瞭などの特徴があります。これらはモンゴリアンデスワームと多くの共通点があり、UMA的な“共通イメージ”として比較されることが多いのです。
作者が明言していなくとも、こうした類似性は読者の想像をかき立てる重要なフックとなっており、『ダンダダン』の世界観の幅広さを物語る要素のひとつとも言えるでしょう。
📖【補足】ミニョコンとは?
ミニョコン(Minhocão)は、ブラジルのUMAで巨大ミミズや蛇のような姿をしているとされる未確認生物。地中を移動し、地震や地割れの原因とされることもあります。モンゴリアンデスワームと同様に“巨大な粘液生物”として、ファンの間で比較対象に挙げられています。
“なんでも吸い込む”妖怪 野づち|ゲゲゲの鬼太郎でも描かれる恐怖の怪異
類似の妖怪として『ゲゲゲの鬼太郎』では、暗がりの穴から突如現れる巨大妖怪・野づちが描かれています。この妖怪は、あらゆるものを吸い込む性質を持ち、動くものも静止物も問わず内部に貪り取りながら成長していきます。
この“野づち”のビジュアルは、巨大ミミズや粘液質のUMAに通じる形状と印象が強く、特にダンダダンのくらがりやモンゴリアンデスワームと重なる部分が少なくありません。視覚的に見る者に不快感と迫力を与える演出が、怪異感として非常に共鳴します。
――主な共通点――
- 地中や暗がりからの出現シーン
- ぬめっとした質感・吸引力のある描写
- 巨大化しつつ対象を飲み込む、強迫的な行動
直接の引用や意図的な参照は明言されていませんが、妖怪とUMAが“恐怖の原型”でつながる視覚表現として、比較する意味は十分にあります。
くらがりとモンゴリアンデスワームの能力・設定を比較してみた
モンゴリアンデスワームの能力は、単なるUMA設定にとどまらず、日本の「くらがり」伝承に重なる要素が多数存在します。
この章では、それぞれの特徴を一つずつ比較しながら、「なぜくらがりと呼ばれたのか?」という核心に迫ります。
特に毒液・粘液といった攻撃手段、異能的な攻撃方法、外見の不気味さなどを切り口に、“共通点”と“演出意図”の両面から考察を進めていきます。
毒液・粘液噴出と甘酒のような描写の共通性
『ダンダダン』作中でモンゴリアンデスワームが吐き出す粘液は、敵を絡め取り、行動不能にさせるほど強力なものでした。この能力はUMA設定の一部でもありますが、日本の妖怪伝承においても非常に似た描写が存在します。
たとえば、くらがり沢やくらがり淵に登場する大蛇は「甘酒のような液体を吐く」とされ、それに触れた者は動けなくなったり、正気を失ったりするという記述があります。液体という“物理的に気持ち悪い”要素に、精神的な不気味さを上乗せしている点が共通しているのです。
単なる攻撃ではなく「存在の不気味さ」を象徴する液体描写は、妖怪としての“くらがり”とUMAとしての“デスワーム”をつなぐ重要な要素となっています。
念波/電撃能力と伝承における怪異性の一致
モンゴリアンデスワームは粘液攻撃に加え、「念波」や「電撃」といった能力も発揮しています。これはUMA設定では“電撃を放つ”という一説から来ていますが、日本の怪異伝承では、こうした能力は“呪術”や“霊的攻撃”として表現されることが多いのです。
つまり、『ダンダダン』のモンゴリアンデスワームは、西洋的な科学的恐怖(電撃)と、日本的な霊的恐怖(念波・呪波)を両立しており、“怪異の現代化”の象徴的キャラとも言えます。
伝承的には「目を合わせるだけで気絶する」「近づくだけで病気になる」などと語られた怪物たちと重なるため、こうした設定もくらがりの正体説を裏付ける要素になります。
UMA=妖怪という構図の面白さ:ダンダダンが描く“境界の怪異”
『ダンダダン』は、UMAと妖怪を単純に分けることなく、“恐怖の根源”としてひとつの存在に融合させています。これは非常に現代的なアプローチであり、妖怪=過去の迷信、UMA=科学的好奇心という従来の枠を超えた描写として秀逸です。
そもそも妖怪もUMAも、人間が理解できないものを“何か”として捉えるために作られた概念です。暗闇に潜む未知、生物とは思えない現象、語り継がれる不気味な存在──それらに名前を与え、恐怖を定義したのが妖怪やUMAなのです。
『ダンダダン』のモンゴリアンデスワームはその代表格であり、日本の「くらがり」伝承と中央アジアの未確認生物という両者の“未知性”を掛け合わせることで、「妖怪=UMA」という視点の転換を提示しています。
この境界のあいまいさは、現代のオカルト・ホラー・都市伝説ジャンルの核心でもあり、『ダンダダン』が単なるバトル漫画にとどまらず、カルチャー的深みを持っている理由のひとつです。
結論:ダンダダンにおける「くらがり」の呼称が意味するもの
『ダンダダン』において、モンゴリアンデスワームが「くらがり」と呼ばれたのは、単なる思いつきやネタではなく、作者が周到に組み込んだ“文化的伏線”でした。ターボババアのセリフは、単なるギャグではなく、彼女の過去の知識や恐怖体験から自然に出た反応であり、日本の大蛇伝承とのリンクによって物語世界の厚みを生んでいます。
特に、四国や長野に伝わる「くらがりの大蛇」伝承との共通点はあまりにも多く、毒や粘液、異常な巨大さ、異界からの襲来などの点で一致しています。さらにUMAとしてのモンゴリアンデスワーム、南米のミニョコン、そして妖怪「くらがり」を一つに融合した存在として描かれた点は、ジャンプ漫画らしい世界観の構築力を感じさせます。
くらがりとは、“名前のない恐怖に対して人々が名付けたもの”であり、モンゴリアンデスワームの存在がそれに重なることで、読者の想像力を掻き立てます。フィクションと伝承が交錯する瞬間に生まれる興奮と不気味さ──まさに『ダンダダン』らしさが詰まった演出でした。
【参考リンク】
ダンダダン公式サイト
ダンダダン公式X
◆ポイント◆
- ターボババアの発言「くらがり」は伏線
- 伝承の「くらがり大蛇」との共通性が鍵
- モンゴリアンデスワームはUMA由来の設定
- 妖怪とUMAの境界を描いた演出が秀逸

記事を読んでいただきありがとうございます!
モンゴリアンデスワームと「くらがり」の関係は謎めいていて、本当に惹き込まれますよね。
妖怪とUMAが交差する『ダンダダン』の世界観、これからも一緒に楽しみましょう!
SNSでのシェアや感想もお待ちしています!